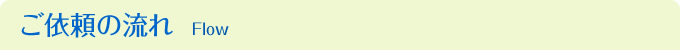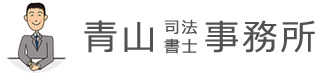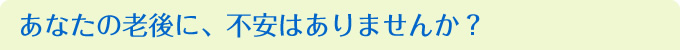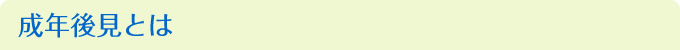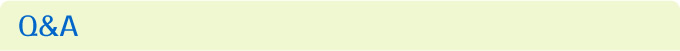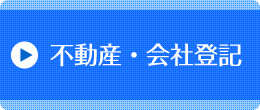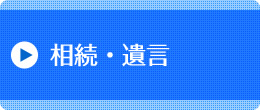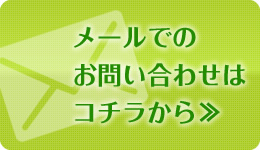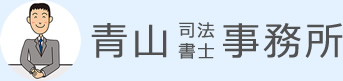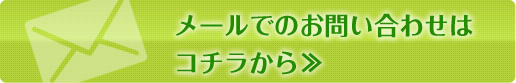最近よく耳にするようになった「成年後見」という言葉。
「後見」というのは、文字どおり「後ろから見守る」ということですが、
一般には分かりづらい制度ではないでしょうか。
私は、「成年後見」を、利用される方の「生活の質」ひいては「人生の質」を高めていく制度であると理解しております。
たとえば、こどもが独立して、家庭を構えた後に、親子兄弟間の行き来が思うに任せなくなり、家族の密なコミュニケーションが取れなくなったとき、親子間、兄弟間の感情の行き違いから、思い煩うことが多
くなります。
ご本人の判断能力が衰えてきたときに、専門職の後見人に財産管理を委ねて、ご本人の生活の質を守るために、在宅や施設の介護サービス、医療のサービスが適正に行われているかどうかを後見人がチェックする成年後見の契約をしておくことにより、「思い煩い」から解放されて、落ち着いて、安心して暮らすことができるようになります。
青山司法書士事務所を、成年後見を利用するためのよきガイドとしてお役立てください。
認知症を発症し、判断能力が衰えて、いろいろなことが分からなくなってきたときにも、自分らしく過ごすことができるように、後見人が支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類あります。
法定後見とは
法定後見は、認知症などにより、判断能力が既に失われたか、不十分な状態になり、
自分で後見人を選ぶことが困難になったときに、家庭裁判所が、後見人を選任します。
民法では、法定後見の申立ができる人を、①本人、②配偶者、③四親等内の親族と定めています。
| 本人の 判断能力が 衰えたとき |
法定後見の 申立て |
家庭裁判所が 後見人を選任 |
後見業務開始 | ご本人が 亡くなったとき 後見業務終了 相続人に ご本人の遺産を 引き渡し |
任意後見とは
任意後見は、判断能力がしっかりしているときに、後見人予定者を、自分で選んでおく制度です。
後見人予定者と、後見の内容、報酬、自分の希望などを話し合って、公正証書で契約をします。
| 任意後見契約 | 見守り契約 | 本人の 判断能力が 衰えたとき任意後見監督人選任 見守り契約終了 |
任意後見業務 開始 |
ご本人が 亡くなったとき任意後見業務終了 亡くなられた後の 事務死後事務委任契約 |
たとえば、このようなときにご相談ください
・身寄りがいません。判断能力が衰えても、自分らしい生き方がしたい…
・子どもはいますが、子どもに頼らない自分らしい生き方をしたい…
・最近、親が高額のものを次々と買ったり、不要なリフォーム工事を依頼している様子なので心配です…
・知的障害、精神障害の子どもがいるが、自分が亡くなった後の我が子の将来が心配です…
- Q1
- お金はどれくらいかかるのでしょうか?
- A1
-
法定後見の場合、後見人の事務費用や報酬は、本人の財産から支払われますが、
報酬額の決定は、資力その他の事情によって、家庭裁判所が行います。
任意後見の場合、依頼者の事情に応じて、契約の中で決定します。
- Q2
- 誰が後見人になるのでしょうか?
- A2
-
親族の中に適任者がいる場合、親族が後見人になることができます。
ただし、家庭裁判所の判断により、法律や福祉の専門家を選任する場合もあります。
適任者がいない場合は、青山司法書士事務所でも、成年後見業務に
取り組んでおりますので、お気軽にお問い合わせください。
- Q3
- 後見人は身元引受人になってもらえるのですか?
- A3
-
後見人は、施設に入所する場合の身元引受人や保証人になれません。
ただし、施設が身元引受人等を求める理由は、退去時や、
施設利用料の不払い時の対応を求めるためです。
退去後に新たに入所する施設等を探したり、
本人の財産から滞りなく施設利用料を支払うなどの職務は、後見人が行います。
後見人が就任することにより、身元引受人の役割は不要となります。
- Q4
- 代理権について教えてください。
- A4
-
後見人は、本人に代わって、契約を行ったり、必要な支払いを行います。
保佐人、補助人は、本人の同意を得た範囲内で、同意権や取消権が与えられます。
さらに、本人の同意と裁判所の審判を得たうえで、一定の範囲内で、
代理権が与えられる場合があります。
任意後見人は、契約の中で、任意後見人に依頼したい事項を決めます。
任意後見人は、契約で決められた範囲内で職務を行います。
- Q5
- 取消権について教えてください。
- A5
-
後見人は、本人を守るために必要があれば、本人の行った行為を取り消すことができます。
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は、取り消しできません。
たとえば、本人が、悪徳商法にひっかかってしまい、不要なものをたくさん
購入してしまった場合には、後見人は、本人の行った契約を取り消して、
悪徳業者に対して、代金の返還を請求することができます。
保佐人は、民法で、保証人の契約など、
重要な財産行為と定められたいくつかの行為について、
保佐人の同意を得ずに行われた本人の行為を取り消すことができます。
民法で、重要な財産行為として定められていない行為についても、本人と相談のうえ、
追加で定めることができます。
補助人は、本人の同意と裁判所の審判を得たうえで、本人の財産行為について
同意権と取消権が与えられる場合があります。
- Q6
- 後見人にできないことはありますか?
- A6
-
後見人は、手術や輸血、延命措置などの医療行為の同意、結婚、離婚、
養子縁組の同意や代理は、行いません。
本人を、実際に介護する行為も行いません。
ヘルパーの介護を受けるため、介護契約を結ぶことが、後見人の仕事です。
また、後見人の職務は、本人の死亡のときまでです。
葬儀等については、原則として、親族が行います。
なお、任意後見契約を締結する場合に、任意後見契約と併せて、死後事務委任契約を
締結することで、葬儀等についても、任意後見人予定者に依頼することができます。
- Q7
- 父の後見人になって、相続対策をしたいのですができますか?
- A7
-
後見人に就任すると、父親の財産を、父親のために管理します。
相続対策は、相続税の節税対策として、父親の存命中に行うものですが、
相続人の利益のために行うものであると考えられます。
後見人は、父親本人の利益のために職務を行いますので、
相続対策を行うことはできません。
- Q8
- 兄の成年後後見人に司法書士が選ばれました。
今までずっと私も兄の財産を把握していたのですが、
後見人は教えてくれません。
- A8
-
後見人の立場としては、親族であっても、本人の財産を開示することには、原則として、
消極的にならざるを得ません。
どうしても知る必要がある理由があるにもかかわらず、
後見人より開示を受けられない場合は、家庭裁判所に開示請求を行うことができます。
家庭裁判所が必要性を認めた場合にのみ、開示を受けることができます。
なお、本人が亡くなった後は、後見人は、家庭裁判所に終了の報告をした後に、
相続人に財産の報告と引渡しを行います。
- Q9
- 後見人の横領事件を聞きます。
親族以外の他人が後見人になっても大丈夫でしょうか?
- A9
-
家庭裁判所は、適正に職務を行うように、後見人を監督しています。
後見人は、家庭裁判所から後見事務の報告を求められたときは、定められた期限内に、
本人の財産状況、収支などを、家庭裁判所に報告しなければなりません。
なお、青山司法書士事務所が所属する、
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートでは、所属会員が適正に職務を
行うための取り組みとして、全会員に定期的な報告を義務付けて、
会員の監督を行っています。
- Q10
- 見守り契約とは、どのようなものですか。
- A10
-
任意後見人予定者が、任意後見開始前に、
基本的には、1カ月に1回、面会して、ご本人の状態を確かめます。
同時に、何か心配事があるかどうかを確かめ、相談を受けます。
将来、任意後見を行うときが来たら、
どのようにして欲しいのかについても聞き取りを行います。
任意後見契約を結ぶときには、さらに、「見守り契約」も結んでおかれるのが、
よいと思います。
- Q11
- 死後事務委任契約とは、どのようなものですか?
- A11
-
ご本人が亡くなったときに、後見人の仕事は、終了しますが、お葬式、
お墓のことなどを頼む親族が見つからないときは、引き続き、死後事務について、
後見人予定者に依頼する旨の契約をしておくことができます。